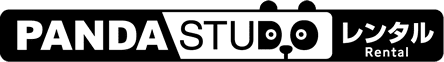【三脚解説シリーズ Vol.1】写真用三脚と動画用三脚の主な違い
この記事の内容

いつもパンダスタジオレンタルをご利用いただき、ありがとうございます。自称「三脚ソムリエ」のスタッフSです。
最近はビデオカメラだけでなく、キヤノンEOSシリーズをはじめとする一眼レフカメラや、SONY αシリーズやコンパクトシネマカメラのFX3やFX6、PanasonicルミックスGシリーズといったミラーレスデジカメ等でも動画撮影される方が増えてきております。
ただ、デジタルカメラの仕様は良く分かっていても、三脚に気を使う方はそれほど多くないのではないでしょうか。
カメラが高性能化していく中で、三脚をしっかりしたものを使わないと、せっかくの画がガクガクになって台無しになってしまいます。4K, 8Kの撮影を行うのであれば、カメラを支える三脚の特性もしっかり理解する必要があるのではないでしょうか。
そこで、今回は「写真用三脚」と「動画用三脚」では何が違うのか、概要をご説明をいたします。
写真用三脚と動画用三脚の特性
写真用三脚の特性
一瞬の時間を切り取るので、カメラのアングル調整のスピードや、瞬間的な固定力に重点を置かれています。また移動を前提としており全般的に重量が軽いです。エレベータ機構があり、高さの微調整が可能です。また、縦アングル撮影にも対応します。
動画用三脚の特性
長時間撮影にも耐えられるよう、カメラマンに負担がかからないようサポートする機能に優れています。プロ用になると100kg超のカメラシステムも支えられます。ヘッドを動かすときも、一定の粘り感があり使いやすいです。ただし、これらの機能を搭載するためにヘッドの構造が複雑化することから、写真用三脚と比べて重量が重くなる傾向があります。また、ヘッドの底面はハーフボール状になっており、水平を素早くとることができます。したがって、動画を撮影するのであれば、「動画用三脚」を利用すべきだと思います。
動画用三脚だけが持つ主な機能
①カウンターバランス機構
ヘッドに内蔵されたスプリング機構により、カメラを水平方向に持ち上げる機構です。これにより、三脚のヘッドのロックを緩めた際にも、カメラは急に下に垂れることがありません。また、カメラマンは少しの力でカメラを動かせます。高価なモデルはこの力の調整が可能です。
②トルク機構
グリスやオイル等の力でヘッドが滑らかに動かせます。この機構がないと、ヘッドを動かすときに抵抗感がなくスカスカとなってしまい、一定のスピードでカメラを動かすことができず、ガクガクの見づらい画となってしまいますので、動画用三脚には必須の機能となっております。高価なモデルはこの力の調整が可能です。
③ツインパイプ機構
多くのビデオ三脚が搭載している2本の脚で支える機構です。シングルパイプ機構よりも安定性が高いことや、ヘッドを動かした際のねじれが起こりにくいために、ヘッドの動きを止めたときに発生する画像の揺り戻しを最小限にとどめる事ができます。
次回のお知らせ
動画用三脚の仕様の見方を次回のブログで解説させていただきます。
【バックナンバー】映像関連の解説シリーズ
もっと映像関係の知識を知りたい!と思った方、パンダスタジオでは映像関係の解説シリーズをブログ形式で紹介しております。下記ブログへの訪問どうぞ!よろしければ高評価ボタンもお願いします!